私たちの身体を包む皮膚のすぐ下には、見た目以上に複雑で精密な構造が存在しています。それが皮下組織と浅筋膜(superficial fascia)です。
この領域は、近年の研究により構造・機能が再評価されており、特に身体運動・リンパ・感覚の調節機構との関連が注目されています。
🔍 皮下組織は「層構造」をもつ?
以前は曖昧だった皮下組織の構造ですが、現在では以下のような3層構造として捉える考え方が広がっています。
-
SAT(浅脂肪組織)
-
浅筋膜(superficial fascia)
-
DAT(深脂肪組織)
この構造は、脂肪の分布・皮膚と筋膜の連結・神経や血管の通り道といった様々な面で非常に重要です。
🧈 SAT:浅脂肪組織とは?
SATは皮膚の直下に広がる層で、以下のような特徴があります。
-
大きな脂肪小葉と垂直な線維中隔から構成
-
体幹では均一に分布、下肢で特に厚くなる傾向
-
汗腺・毛包・パチニ小体などの構造を含む
-
皮膚と筋膜を連結しつつ、クッション性や断熱性を担う
🎯 浅筋膜の役割と構造
SATとDATの間にある線維層が「浅筋膜」です。
一見薄い膜のようですが、実はとても重要な結合組織です。
-
コラーゲン線維と弾性線維が緩やかに混在
-
浅皮膚支帯・深皮膚支帯という線維中隔を介して、皮膚・筋膜と連結
-
一部で静脈・リンパ管・神経の通路や区画形成に関与
-
**感覚受容器(ルフィニ小体、パチニ小体)**も存在
-
体温調節、血流調整、感覚認知に関与する
🧈 DAT:深脂肪組織とは?
SATの下にあるDATは、構造も機能も異なります。
-
構造はやや緩く、斜め方向の線維中隔をもつ
-
可動性の高い滑走層として機能し、筋と皮膚の動きを分離
-
通常、SATより薄くて変動が大きい
🔩 付着構造:皮膚と筋膜がくっつく場所
◽ 縦走付着
-
正中線(白線・帽状腱膜など)で浅筋膜と深筋膜が縦方向に融合
◽ 横走付着
-
関節周囲で見られ、皮膚を骨にしっかりと固定
-
屈筋部や鼠径部、耳前方、腸骨稜などに存在
👶 胎児〜新生児における発達
-
胎児5〜6ヶ月頃から浅筋膜が明瞭になり、SAT・DATに分離
-
8ヶ月頃には皮膚支帯が脂肪を区画化し始める
-
新生児のSATは脂肪が豊富だが、構造は柔らかく、支帯は成人より太くても弱い
-
出生後20週以降、浅筋膜に褐色脂肪組織が多く見られる
⚙️ 機械的特性と機能の違い
| 層 | 主な機械的・生理的機能 |
|---|---|
| SAT | ソリッド構造を形成し、皮膚を保護 |
| 浅筋膜 | 感覚・循環・体温調整の要 |
| DAT | 可動性の高い層で、運動によるずれを吸収 |
| 層 | 特化した機能 |
|---|---|
| 浅筋膜 | 体温調節、リンパ流・静脈循環、皮膚認知 |
| 深筋膜 | 固有感覚、運動の協調制御 |
🩸 血管・神経・滑液包
-
皮下血管(動脈・静脈・リンパ管)は主に浅筋膜に沿って分布
-
神経受容器はSATと浅筋膜内にあり、皮膚の伸張・圧覚を感知
-
皮下滑液包(皮下包)はDAT内で、浅筋膜と深筋膜の摩擦緩衝として存在
📝 まとめ
皮下組織と浅筋膜は、単なる「脂肪の下の膜」ではありません。
それぞれの層が明確な役割を持ち、身体の保護・感覚・滑走性・循環などに重要な貢献をしています。
とくに浅筋膜は、感覚・体温・循環という面で想像以上に機能的な役割を果たしているのです。
次回は「深筋膜」について詳しく解説します。お楽しみに!

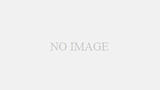
コメント